資産運用とは何?どうやって始める?
初心者向けに基本知識・注意点をカンタン解説
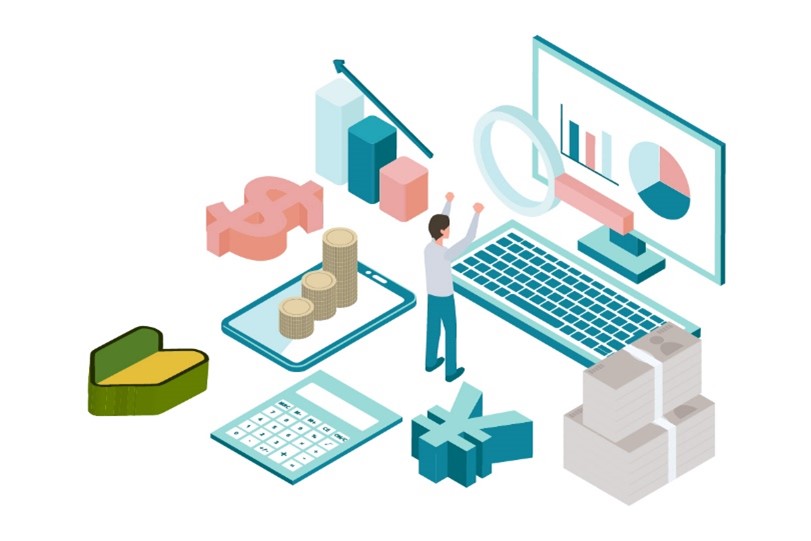
- このページに掲載している保険商品の内容は、一般的と考えられる内容です。
また、記事中で掲載している保険商品に関して、当社では取扱いのない保険商品もあります。
各保険会社が取扱う保険商品の内容については、各保険会社へお問合せください。
近年、資産運用が注目されています。その理由の一つに、人生100年時代と言われるように、退職後に長い老後生活があり、年金のみで暮らしていくことへの不安があります。
また、NISA(ニーサ。少額投資非課税制度)・iDeCo(イデコ。個人型確定拠出年金)等の制度が始まり、拡充もされたため、個人での投資がしやすい環境になったことも大きな要因といえるでしょう。
こうした環境の変化に伴って、ニュース等でも資産運用が話題になることが増えました。それでも、「難しそうで始められていない」「始めたけれど自信がない」「今さら聞けない」といった方もいるのではないでしょうか。
今回は、そんな資産運用初心者の皆さんに向けて、基本からわかりやすくお伝えしていきます。
- 資産運用とは金融商品等を活用して、効率的にお金を増やすことである。
- 金融商品には、株式・債券・投資信託・保険等があり、それぞれにメリット・デメリットがあるので、特性をよく理解したうえで選択する必要がある。
- NISAやiDeCoといった税制優遇制度についても知っておくと有利。
- 資産運用の際は、投資の基本となる考え方である「長期・積立・分散」を理解しておこう。
資産運用とは?なぜ注目されている?
「資産運用」は、株式・債券・投資信託・保険といった金融商品等を利用して、効率的に資産を増やすことを意味します。すでに手元にある資金の一部で金融商品等を購入し、その運用成果によって利益を得ることを目指します。
自分が働いてお金を得るのでなく、金融商品等から利益を得ることから、「お金に働いてもらっている」という言い方もできるでしょう。
ただし、資産運用では必ずしも利益が出るとは限らず、元本割れをする可能性があることも知っておかなければなりません。
資産運用が注目されている理由
昨今、資産運用が注目されている背景には、いくつもの要因がありますが、主に以下のものが挙げられます。
- 少額から投資しやすくなった
- 非課税で投資できる額が増えた
- インフレによる物価高
少額から投資しやすくなった
資産運用はお金持ちがするもの、というのは一昔前の話です。まとまったお金がなくても少額から投資がしやすい環境が整ったことで、資産運用のハードルが下がっています。
例えば、今では株式や投資信託等も、金融機関によっては100円程度から購入できるので、毎月5,000円ずつ積立てる等、自分の収入に合わせてコツコツと投資していくことができます。
非課税で投資できる額が増えた
NISAが2024年1月から拡充しました。詳しくは後述しますが、NISAが新しくなったことで、非課税投資の上限額が年間360万円まで拡大しています。
インフレによる物価高
高級品だけでなく、生活に欠かせない食料品や光熱費までが値上がりを続けています。
物の値段が上がるということは、それまで1,000円だったものを買うのに1,000円より多く払わなければならなくなるように、物に対するお金の価値が低下することを意味します。
例えば、自販機の缶ジュースを思い浮かべてみましょう。
昔は80円や100円で買える自販機を多く見かけたかと思いますが、今では価格が130円や150円になっている自販機を見ることが多いでしょう。
価格が変わらない預金には安心感がありますし、お金を守っているように見えますが、物価上昇時には、現金や預金でお金を持っているだけでは、お金の価値が目減りしていきます。
物価高が続く中では、お金に働いてもらう必要性が高まっています。
資産運用の種類にはどんなものがある?
自分で働いて稼いだ賃金等を銀行や郵便局、信用金庫等に預けている方は多いのではないでしょうか。
これらの普通預金(普通貯金)には、必要なときにお金をすぐに引出せる流動性と、元本割れしない安全性があることが大きな特徴です。
しかし、現在の日本の低金利ではほとんど利息が付かないため、預貯金だけで資産を大きくしていくことは、かつてよりも難しくなっています。
そのため、資産運用によってお金を増やしていく必要性が高まっているといえるでしょう。
資産運用をしてお金に働いてもらうためには、預貯金の中から、金融商品等を購入することが必要です。
ここからは、資産運用に利用される代表的な商品の種類とその特徴、メリット・デメリットについてご紹介します。
株式
株式会社に出資をして株主になることを株式投資といいます。株式市場に上場された株式を購入すると、株主となり、企業が生んだ利益の一部を配当金として受取ることができます。市場での取引によって株価は常に変動しているため、株価が上がったタイミングで売却すれば売却益を得ることができます。
一方で、保有する株式の値段が下がる可能性もあり、そのタイミングで売却した際には売却損が発生することになります。
債券
債券とはお金の借用証書のようなものです。国や地方自治体・企業等が、投資家からお金を借りるために、「国債」「地方債」「社債」といった有価証券を発行します。
満期までの間、投資家は定期的に利子を受取ることができ、満期を迎えると、当初貸出した額面の金額が戻ってきます。
注意点は、投資先が破綻した場合、貸したお金が戻ってこない可能性があることです。そのため、信用できる投資先を選ぶことが重要になります。
不動産
不動産投資は、アパートやマンションを購入して人に貸出し、家賃収入を得ることです。安定して貸出せれば、毎月一定額の家賃収入を得られるので、その家賃収入を購入時に借りたローンの返済にも充てられます。
ただし、金融商品とは異なり、物が存在しているので、築年数が古くなればその分資産価値は下がります。また築年数が古くなることにより、需要が下がってしまうと、借主がいない空室期間ができてしまい、その間は家賃収入が途絶えます。そのほか、入居者から家賃が支払われない滞納リスク等もあります。
投資信託
投資信託は、株式や債券等を複数組合わせて少額から購入しやすくした金融商品です。運用会社の立てた投資戦略に賛同した多くの人から集めたお金で、いくつもの投資先に分散して投資します。
運用で利益が出ると、お金を出した割合に応じて利益が分配されるほか、値上がりしたタイミングで売却すれば売却益を得られます。少額から始めやすく、投資先を分散でき、積立購入もできるため、資産運用の初心者やまとまったお金がない人にも始めやすいでしょう。
しかし株式や債券と同様に、元本割れリスクはあるので、リスクをどれだけ許容できるかで、投資先のファンドを選択するとよいでしょう。
保険
貯蓄性のある保険では、いざというときの保障を備えながら資産形成ができます。保険期間中に被保険者に万一のことがあれば、死亡保険金が支払われます。
また、保障が不要になり中途解約をして解約払戻金を受取れば、子どもの教育費・老後資金等として活用できます。ただし、解約のタイミングによっては払込保険料総額を下回ることがあるので、契約内容をよく確認することが重要です。
貯蓄性の保険には、終身保険・養老保険・個人年金保険・学資保険等がありますが、より資産運用の要素が大きい保険に、変額保険もあります。
変額保険では、契約者が払込む保険料の一部を株式や債券等で運用し、その運用の成果によって死亡保険金や解約払戻金等の額が変動します。なお、変額保険は元本割れリスクのある商品なので、仕組みを理解しておく必要があります。
最近よく聞く「NISA」「iDeCo」って何?
投資にまつわる用語で最近よく見聞きする言葉に、「NISA(ニーサ。少額投資非課税制度)」「iDeCo(イデコ。個人型確定拠出年金)」があります。それぞれの言葉の意味や基本的な特徴、利用時の注意点等について解説します。
NISAとiDeCoの主な違い
| NISA | iDeCo | |
|---|---|---|
| 投資目的 | 自由 | 老後資金 |
| 資金の引出し | いつでも可能 | 原則60歳以降 |
| 投資・拠出上限額 | 生涯で1,800万円 | 年間144,000円~816,000円※ |
| 投資対象商品 | 上場株式・投資信託等 | 投資信託・定期預金・保険商品等 |
| 主な税制優遇 | 運用益が非課税 |
|
※加入している国民年金の種類や企業年金の有無により異なります。
NISAとはどんな制度?
NISAは個人の投資を後押しする制度で、投資で得た利益に税金がかからないメリットがあります。
本来、投資で得た利益には約20%の税金がかかりますが、NISA口座で投資をすれば税金が差引かれない分、より多くのお金を手元に残すことができます。
| つみたて投資枠 | 成長投資枠 | |
|---|---|---|
| 非課税保有期間 | 無制限 | 無制限 |
| 口座開設期間 | 恒久化 | 恒久化 |
| 年間投資枠 | 120万円 | 240万円 |
| 非課税保有限度額(総枠) | 1,800万円
※このうち、成長投資枠は最大1,200万円まで |
|
| 投資対象商品 | 長期・積立・分散投資に適した一定の投資信託(金融庁の基準を満たした投資信託に限定) | 上場株式・投資信託等 |
| 対象年齢 | 18歳以上 | 18歳以上 |
※つみたて投資枠と成長投資枠の併用ができます。
従来は期間限定の制度として「つみたてNISA」「一般NISA」等がありましたが、2024年1月からはこれらが1つの制度となって、一生にわたって非課税投資ができる恒久的な制度となりました。
さらに、「つみたて投資枠」と「成長投資枠」は併用可能で、非課税投資可能額が1年間では最大360万円まで、一生涯では1,800万円まで拡大しています。利用目的に制限がなくいつでも出金できる自由さがあります。
ただし、株式や投資信託等による利益は非課税になりますが、リスクがなくなるわけではありません。
NISAにおいても元本割れの可能性があることは理解しておきましょう。
iDeCoとはどんな制度?
iDeCoは、公的年金とは別に給付を受けられる、私的年金制度の1つです。
希望者が任意で加入して、掛金の拠出、運用を自分で行い、掛金と運用益との合計額から、将来、給付を受取ります。
投資商品を購入した場合はNISAと同じく、元本割れのリスクがあることは把握しておく必要があります。
iDeCoの最大のメリットは、掛金拠出時・運用期間中・受取り時と、3つのタイミングで税制優遇が受けられることです。
デメリットとしては、口座開設時等に手数料がかかること、受取りが原則60歳以降と決まっていて、途中で引出しができないことが挙げられます。
ロボアドとはどんなもの?
近年注目され始めている「ロボアド」とは、ロボットアドバイザーの略称です。AI技術によって、投資のアドバイスや運用等が行えます。
年齢、投資経験、金融資産、投資目的、性格等のいくつかの質問に答えると、AIがリスク許容度を判定し、おすすめの資産配分を教えてくれます。
ロボアドの中には、投資のアドバイスにとどまらず、おすすめの資産配分に合わせて投資ができるものもあります。
ただし、サービスによってNISAやiDeCoへの対応可否が異なることや、運用にかかるコストが高めな場合があること、元本割れといった損失が発生しても補償がないこと等に注意が必要です。
資産運用を始める前の注意点
資産運用では、値動きのある金融商品等を売買するため、値上がりの可能性に期待できる反面、値下がりの可能性も伴います。
損失をなるべく防ぐために、資産運用を始める前に知っておくべき基本的な考え方と注意点を紹介します。
目的を明確にする
何のための資産運用なのか、目的を明確にしましょう。
例えば、運用目的には老後資金や住宅購入、子どもの教育資金等があるでしょう。
目的によって、運用期間や許容できるリスクが変わるので、それに合わせた運用をしましょう。
余裕資金で運用する
資産運用の大原則として、すぐに使う予定がない、余裕資金で行うようにしましょう。これは、すぐに使う目的が決まっているお金は減らさないことが重要なためです。
値動きがある商品は、順調に価格が上がる時もあれば、購入時よりも価格が下がって元本割れする可能性もあります。
すぐに使う予定のない余裕資金であれば、価格が下がっても次の値上がりを待つことができるでしょう。
分散投資を心掛ける
投資の格言に「卵は一つのかごに盛るな」という言葉があります。
大切な卵を一つのかごに盛ると、かごを落とした時にすべてが割れてしまうことから、大切な資産を一か所にまとめず、いくつもの投資先に分けることの大切さを伝えることわざです。
分散投資を心掛けましょう。
購入タイミングを分ける
投資先を分けるだけでなく、購入のタイミングも何度かに分けましょう。値動きのある商品を一度にまとめて購入すると、高値のときにまとめ買いしてしまう可能性があるからです。
その点で、毎月一定金額ずつ自動購入する積立投資は、高値のときには少なく、安値のときには多く買うことになり、購入価格が平準化されるというメリットがあります。
長期・積立・分散が始めやすく続けやすい
積立なら、毎月一定金額ずつ自動的に購入ができるので手間がかかりません。さらに、積立で購入するものが、投資信託のようにさまざまな株式や債券等に分散投資できるものであれば、手軽に分散投資ができます。
投資信託の積立購入を長期間にわたって淡々と続けることで、長期・積立・分散投資が可能になります。
投資信託を使った長期・積立・分散投資は、NISAやiDeCoの制度を使っても行えます。また、死亡保障等の付いた変額保険でも長期・積立・分散投資をすることができます。
資産運用以外にもリスクへの備えが必要
人生では予測できないことが起こりえます。死亡や高度障害のリスクのほか、病気やケガ等健康上のリスクにもあらかじめ備えておくと安心です。
若いうち、元気なときは、あまりこうしたリスクのことは考えないかもしれません。
しかし、あらかじめ医療保険やがん保険等で備えておけば、実際に病気やケガをしてしまい治療費がかさんだとしても、せっかく築いた資産を大きく取り崩さなくて済むでしょう。
また、資産運用をしていると、相場によって資産価値が上下するため、万一のときに相場が悪いと、大切な家族にのこせる資産が少なくなってしまうリスクがあります。
こうした場合でも、一定の死亡保障を備えることで安心につながるでしょう。
資産運用は効率的にお金を増やすこと。すぐに使わないお金で少しずつ行おう
「資産運用」は、手元にある余裕資金で金融商品等を購入して、新たな収益を目指すことを言います。
現金を大切に守るだけではお金の価値が下がってしまう今こそ、お金に働いてもらい効率的にお金を増やすことも考えていきましょう。
資産運用を考える中で、保障も必要と感じたときには、運用の一部で保険を活用することを検討してみましょう。
ただし、資産運用には元本割れのリスクも伴います。長期・積立・分散投資を心掛けましょう。
- 変額保険は国内外の株式・債券等で運用をしており、運用実績が保険金額や積立金額・年金額等の増減につながるため、株価や債券価格の下落、為替の変動により、積立金額、解約払戻金額等が既払込保険料の累計額を下回ることがあり、契約者に損失が生ずるおそれがあります。また、保険関係費、運用関係費、解約・減額時にかかる費用等を契約者にご負担いただきます。詳細は「商品パンフレット」等をご確認ください。
- 記載の内容は、2024年12月現在の税制・関係法令等に基づき税務の取扱等について記載しております。今後、税務の取扱等が変わる場合もございますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。個別の税務の取扱等については(顧問)税理士や所轄の国税局・税務署等にご確認ください。
- このページに掲載している保険商品の内容は、一般的と考えられる内容です。
また、記事中で掲載している保険商品に関して、当社では取扱いのない保険商品もあります。
各保険会社が取扱う保険商品の内容については、各保険会社へお問合せください。 - 本記事は、当社からファイナンシャルプランナーに依頼し執筆いただいた原稿を、当社で編集したものです。
- [注1] 厚生労働省「iDeCoの概要」
- [注2] 金融庁「NISAを知る」
【執筆者プロフィール】

氏家 祥美(うじいえ よしみ)
ファイナンシャルプランナー/キャリアコンサルタント
ハートマネー代表
www.heart-money.net
旅行好きで「遊びゴコロあるライフプランを共に作る」がモットー。2005年からFPとして活動し、高校家庭科の教科書執筆や大学の非常勤講師等、金融リテラシーの普及にも務める。
-
資料を見て
資料請求
じっくり検討 -
専門スタッフに
電話(通話料無料) 0120-8739-13
無料相談
(通話料無料)
電話受付
時間
月〜金 9:00〜19:00/土日 9:00〜17:00
(祝日、12/31〜1/3を除く)