貯蓄の平均額はいくら?
年代別平均貯蓄額と、上手にお金を増やすコツを解説!

- このページに掲載している保険商品の内容は、一般的と考えられる内容です。
また、記事中で掲載している保険商品に関して、当社では取扱いのない保険商品もあります。
各保険会社が取扱う保険商品の内容については、各保険会社へお問合せください。
「お金が貯まらない」「自分の今の貯金額で、将来大丈夫なのか」など、貯金について不安を感じている人もいるでしょう。
自身のライフステージや家族構成、もしくは将来の夢や目標によっても必要な金額は異なってきます。
また、病気やケガ、失業など思わぬ出来事があったときにも、貯金があると安心できるでしょう。
この記事では、全国平均データから年代別の貯蓄額や、収入に対する貯蓄の割合について調べてお伝えします。
貯蓄の目安、家計収支の理想的なバランスを知って、家計の参考にしましょう。
- 貯蓄額の傾向は年代・家族構成によって異なるので、自分と同じ属性の人の平均値・中央値等を参考にするべき。
- 結婚・住宅購入・老後資金など、何のために貯蓄をするのか目的を明確化させ、それに合わせた方法や目標金額を決める必要がある。
- 無理なく貯蓄を続けていくためには、家計のバランスが重要。
- 余裕資金があれば、貯蓄だけでなく、お金を増やす「資産運用」も検討を。
年代別・家族構成別の貯蓄額の目安
貯蓄額は、年代・家族構成によってもその傾向は大きく異なります。ご自身と同じ属性の人がどの程度の貯蓄をしているのかを、確認していきましょう。
ちなみに貯蓄額とは、預貯金のみを指さず、株式・投資信託・生命保険等も含めた金融資産保有額を意味します。
それでは、他の人がどのくらい貯蓄をしているのか、データをもとに見ていきましょう。
金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査」のなかから、単身者(ひとり暮らし)と二人以上の世帯の金融資産保有額を年代別にご紹介します。
なお、こちらで紹介するデータは、「貯蓄が無い」と答えた人を除いた、金融資産保有世帯のみの平均値、中央値をご紹介しています。
単身者(ひとり暮らし)の貯蓄額
金融資産保有額(金融資産保有世帯・単身世帯)
| 年代 | 平均値 | 中央値 |
|---|---|---|
| 20歳代 | 219万円 | 103万円 |
| 30歳代 | 912万円 | 300万円 |
| 40歳代 | 964万円 | 500万円 |
| 50歳代 | 2,288万円 | 555万円 |
| 60歳代 | 2,240万円 | 1,100万円 |
| 70歳代 | 2,104万円 | 1,100万円 |
| 全年代の平均 | 1,492万円 | 500万円 |
※平均値…調査対象世帯の保有額をすべて合計して、その世帯数で割った金額。
※中央値…調査対象世帯を保有額の少ない順(あるいは多い順)に並べたとき、真ん中に位置する世帯の保有額。
単身者の貯蓄額の平均値は1,492万円です。20歳代は219万円で、50歳代の2,288万円でピークに達するまで、右肩上がりに増加して、その後は緩やかに減少していきます。
単身者全体の貯蓄額の中央値は、500万円です。20歳代が103万円で、60歳代・70歳代でピークの1,100万円に達しています。
中央値500万円に対して平均値がその3倍近くあることから、一部の人が平均値を上げていることがわかります。単身者の真ん中を意識するのであれば、各年代の中央値が目安となるでしょう。
二人以上の世帯の貯蓄額
金融資産保有額(金融資産保有世帯・二人以上の世帯)
| 年代 | 平均値 | 中央値 |
|---|---|---|
| 20歳代 | 403万円 | 171万円 |
| 30歳代 | 856万円 | 337万円 |
| 40歳代 | 1,236万円 | 500万円 |
| 50歳代 | 1,611万円 | 745万円 |
| 60歳代 | 2,588万円 | 1,200万円 |
| 70歳代 | 2,188万円 | 1,100万円 |
| 全年代の平均 | 1,758万円 | 715万円 |
二人以上の世帯の貯蓄額の平均値は1,758万円です。20歳代は403万円で、60歳代の2,588万円でピークに達するまで右肩上がりに増加し、その後は減少傾向にあります。
二人以上の世帯全体の貯蓄額の中央値は715万円です。20歳代は171万円で、60歳代でピークの1,200万円に達しています。
平均値と中央値で2倍以上の差が見られることから、こちらでも一部の人が平均値を上げていることがわかります。二人以上の世帯の真ん中を意識するのであれば、各年代の中央値が目安となるでしょう。
何のための貯金・貯蓄なのかを意識することが大事
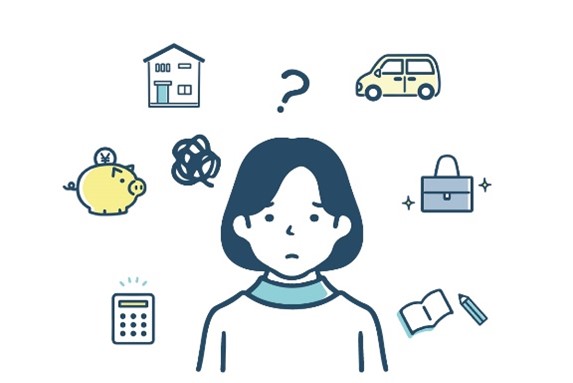
同年代の貯蓄額の目安がわかっても、安心できる金額とは限りません。
何に使うお金なのかをわかっていなければ、貯蓄を続けられなくなったり、必要なときにお金が足りなくなる可能性があります。
貯蓄のモチベーションを上げるためにも、貯蓄の目的や使うタイミングを意識して、それに合わせた方法や、金額を決めていきましょう。
一生の中で、大きなお金が必要になる主なライフイベントには、以下のようなものがあります。
- 結婚
- 子どもの教育
- 住宅購入
- 老後
- 介護
それぞれ、目安となる金額と併せてご紹介します。
結婚
挙式・披露宴・ウエディングパーティー費用の総額は、平均で327.1万円。平均費用はコロナ禍が明けて回復傾向にあり、招待客人数の平均は49.1人です。[注3]
子どもの教育
幼稚園3歳から高等学校第3学年までの15年間の学習費総額
| ケース | お子様ひとりあたり |
|---|---|
| すべて公立に通った場合 | 約574万円 |
| 幼稚園は私立、小学校・中学校・高等学校は公立に通った場合 | 約620万円 |
| 幼稚園・高等学校は私立、小学校・中学校は公立に通った場合 | 約781万円 |
| すべて私立に通った場合 | 約1,838万円 |
※保護者が子どもの学校教育および学校外活動のために支出した経費の総額
国公私立大学の入学料と授業料について(入学年度分)
| 国立大学 | 公立大学 | 私立大学 | |
|---|---|---|---|
| 授業料 | 535,800円 | 536,191円 | 959,205円 |
| 入学料 | 282,000円 | 374,371円 | 240,806円 |
| 合計 | 817,800円 | 910,562円 | 1,200,011円 |
子ども一人にかかる教育費は、公立か私立かの選択によって大きく変わります。
幼稚園から高校までの15年間の教育費総額は、すべて公立の場合は約574万円、すべて私立の場合には約1,838万円です。
さらに、大学進学を予定する場合には、学費をあらかじめ用意しておきましょう。
上述の表では、入学年度分のみの金額となっていますが、実際には大学4年間の費用となるので、授業料は単純に4倍の金額がかかります。
お子さまの将来の可能性を狭めないためにも、教育費は十分に準備しておきましょう。
住宅購入
| 所要資金(平均) | 融資金額(平均) | |
|---|---|---|
| 注文住宅 | 3,863万円 | 3,040万円 |
| 土地付注文住宅 | 4,903万円 | 4,171万円 |
| 建売住宅 | 3,603万円 | 3,092万円 |
| 新築マンション | 5,245万円 | 3,889万円 |
| 中古戸建 | 2,536万円 | 2,182万円 |
| 中古マンション | 3,037万円 | 2,393万円 |
2023年度に住宅ローンフラット35を利用した住宅購入の所要資金の平均は、注文住宅で3,863万円、新築マンションで5,245万円でした。
住宅価格は選ぶ物件のタイプ、地域などによっても大きく異なります。
老後
夫婦二人に必要と考える1ヵ月あたりの老後生活費
| 実収入(平均) | 24.4万円 |
| ゆとりある老後生活費(平均) | 37.9万円 |
老後は、公的年金だけでは足りない生活費を自分で補う必要があります。
65歳以上の夫婦一組の無職世帯の実収入は平均24.4万円、そして、ゆとりある老後生活費は平均37.9万円でした。退職後の期間を仮に20年間とすると、老後の実収入の合計額は5,856万円、ゆとりある老後生活費の合計額は9,096万円。
これらの差額を計算すると、20年間分の不足額は3,240万円となります。
ちなみに老後のゆとりのための上乗せ額の使い道には、旅行・レジャー・日常生活費の充実・趣味・教養等が挙がっています。
介護
介護にかかった費用と時間
| 一時的にかかった費用(平均) | 74万円 |
| 月々の費用(平均) | 8.3万円 |
| 介護にかかった期間(平均) | 5年1か月(61ヵ月) |
生命保険文化センターの調査によると、介護にかかった月々の自己負担費用は平均8.3万円、介護にかかった平均期間は、5年1ヵ月(61ヵ月)です。これらを掛け合わせると、506.3万円となります。さらに、介護にかかった一時的な費用74万円を上乗せすると、介護にかかる費用の目安は、580.3万円と計算できます。
収入のうち、いくら貯蓄に回すべき?
貯蓄の目的がわかったら、毎月貯めていけるように家計管理をしていきましょう。
貯蓄を無理なく続けていくためには、家計のバランスが重要になります。自分と近い年代、ライフスタイルの人が年収のうち、どの程度の割合を貯蓄しているのかを参考にしてみましょう。
年代別貯蓄割合
年間手取り収入(臨時収入を含む)からの貯蓄割合(金融資産保有世帯)
| 年代 | 単身世帯 | 二人以上の世帯 |
|---|---|---|
| 20歳代 | 18% | 14% |
| 30歳代 | 17% | 14% |
| 40歳代 | 14% | 12% |
| 50歳代 | 14% | 12% |
| 60歳代 | 10% | 11% |
| 70歳代 | 6% | 8% |
| 平均 | 13% | 11% |
貯蓄割合(手取り収入のうち、貯蓄に回す金額の割合)の平均は、単身者で13%、二人以上の世帯では11%となっています。年代別にみると、20歳代から50歳代では単身者の貯蓄割合が高く、60歳代・70歳代では二人以上の世帯の貯蓄割合が高くなっています。
現役時代は単身者の方が貯蓄できていますが、仕事をリタイアしてからは、二人分の年金収入がある既婚者世帯の方が貯蓄に回す余裕があると考えられます。
上手にお金を増やすコツ
当面の生活費やリスクに備えるお金は、元本保証でいつでも出し入れできる預貯金でまかなうと安心です。
預貯金の額が大きくなってきたら、「貯める」ことだけでなく、すぐに使わないお金を「増やす」ことも考えましょう。
貯蓄にまわす金額を増やす
貯蓄を増やすためには、収入を増やすか、支出を減らすかですが、収入を増やすのは簡単ではありません。
今すぐ実践できることとして、支出を減らす、もっと言えば固定費を減らしてみましょう。固定費とは、毎月ほぼ一定でかかる支出のことです。例えば、家賃・水道光熱費・通信費・自動車維持費といったものです。
使用していないサブスクリプションサービスを解約するなど、身近なことから実践してみましょう。
上手に資産運用する
預貯金には、「元本が保証されている」「いつでも出し入れできる」というメリットがありますが、貯金しているだけではお金はほとんど増えません。すぐに使う予定のないお金、余裕資金は、資産運用をして「増やす」ことも考えましょう。
資産運用とは、株式・債券・投資信託・保険といった金融商品等を活用して、効率的に資産を増やすことを意味します。手持ち資金で金融商品等を購入して、配当金・分配金・売却益・為替差益等によって、お金が増えることに期待できます。
ただし、資産運用には元本割れのリスクも伴うので、余裕資金で行う必要があります。
資産運用には保険という手段も
資産運用のために保険を活用するという手段もあります。
なかでも貯蓄型保険の一種である変額保険は、万一の保障と資産運用の機能を兼ね備えているため、運用成果次第では、死亡保障額や解約払戻金等の受取額を増やせる可能性があります。
資産運用の概要やNISA・iDeCoといった具体的な資産運用の種類・方法について知りたい方は以下の記事もご覧ください。
自身の生活・ライフプランに合わせた貯蓄・資産運用計画を
全国平均データでは、年収に対する平均貯蓄割合は、ひとり暮らしは13%、既婚者は11%とありました。しかし、その割合を貯蓄していれば安心かというと、実はそうとばかりは言えません。
退職金のある人とない人、ひとり暮らしか既婚者か、これまでの働き方によって、老後の年金収入にも大きな差が出てきます。また、子どもの教育費がこれからかかる人とかからない人など、お金のかかるライフイベントの有無によって支出にも差が出てくるでしょう。
比較的余裕があると思えるタイミングは、あなたにとって貴重な「貯めどき」です。これまでより少し多めに貯めること、資産運用で増やすことも併せて考えていきましょう。
- 変額保険は国内外の株式・債券等で運用をしており、運用実績が保険金額や積立金額・年金額等の増減につながるため、株価や債券価格の下落、為替の変動により、積立金額、解約払戻金額等が既払込保険料の累計額を下回ることがあり、契約者に損失が生ずるおそれがあります。また、保険関係費、運用関係費、解約・減額時にかかる費用等を契約者にご負担いただきます。詳細は「商品パンフレット」等をご確認ください。
- 社会保障制度に関しては2024年12月時点の内容を参考に記載しております。
- 記載の内容は、2024年12月現在の税制・関係法令等に基づき税務の取扱等について記載しております。今後、税務の取扱等が変わる場合もございますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。個別の税務の取扱等については(顧問)税理士や所轄の国税局・税務署等にご確認ください。
- このページに掲載している保険商品の内容は、一般的と考えられる内容です。
また、記事中で掲載している保険商品に関して、当社では取扱いのない保険商品もあります。
各保険会社が取扱う保険商品の内容については、各保険会社へお問合せください。 - 本記事は、当社からファイナンシャルプランナーに依頼し執筆いただいた原稿を、当社で編集したものです。
- [注1] 金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査(単身世帯調査)令和5年調査結果 」
- [注2] 金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査(二人以上世帯調査)令和5年調査結果 」
- [注3] 「ゼクシィ結婚トレンド調査2023調べ」
- [注4] 文部科学省「子供の学習費調査」(令和3年度)
- [注5] 文部科学省「私立大学等の令和5年度入学者に係る学生納付金等調査結果について」(参考2)国公私立大学の授業料等の推移
- [注6] 住宅金融支援機構「2023年度 フラット35利用者調査」
- [注7] 総務省統計局「2023年 家計調査(家計収支編)」
- [注8] 生命保険文化センター「生活保障に関する調査 2022年度」
- [注9] 生命保険文化センター「リスクに備えるための生活設計」
【執筆者プロフィール】

氏家 祥美(うじいえ よしみ)
ファイナンシャルプランナー/キャリアコンサルタント
ハートマネー代表
www.heart-money.net
旅行好きで「遊びゴコロあるライフプランを共に作る」がモットー。2005年からFPとして活動し、高校家庭科の教科書執筆や大学の非常勤講師等、金融リテラシーの普及にも務める。
-
資料を見て
資料請求
じっくり検討 -
専門スタッフに
電話(通話料無料) 0120-8739-13
無料相談
(通話料無料)
電話受付
時間
月〜金 9:00〜19:00/土日 9:00〜17:00
(祝日、12/31〜1/3を除く)