
正しさとやさしさを両立させ「誰も取り残さない」施策を実行したい。はなさく生命のDNAをつくる、人事の仕事
「『ありたい世界』に向かって熱量高く取り組む。でも、通った道に花が咲かなくなってしまうことがないように、やさしさも必要だと思うんです」。人材開発チームにて、人材戦略の検討をメインに採用・育成・企業風土醸成と、幅広い業務を担う人事総務部 課長補佐の大下奈津子。「正しさだけでなく、やさしさも忘れずに、従業員とその先にいる大切な人たちを幸せにしたい」。そう話す大下に、人事業務にかける想いやこれからの組織のあり方について聞きました。

大下 奈津子 NATSUKO OSHITA
人事総務部 課長補佐
東京都出身。2003年に大学卒業後、新卒で総合人材サービスへ入社。人材紹介事業の立ち上げ期に、キャリアコンサルタントとして従事。2回の育児休業を経て、IT通信業界へ転職し、SaaS営業や人事に従事。2023年1月にはなさく生命に人材開発担当として入社。
休日はストレス解消のためボクシングで汗を流す。
目次
- 「自分をさらに高めたい」多様な課題にチャレンジできそうな、はなさくを選ぶ
- 従業員の声に耳を傾け、誰もが活躍できるよう人事施策を整える
- 景色合わせの難しさに苦悩。「健全に意見を交わせる環境のおかげで乗り越えられた」
- 「人事にとってのお客様は従業員」その先にいる家族も幸せに
- 「プロフェッショナルに選ばれるはなさく生命」でありたい
全て表示
「自分をさらに高めたい」多様な課題にチャレンジできそうな、はなさくを選ぶ
はなさく生命に入社する前、大下さんはどんなキャリアを歩んでいましたか?
私は新卒で総合人材サービス企業に入社しました。当時、営業職、広報などの部署で経験を積むなかで、より「自分が思い描くキャリアや仕事を実現できる環境に飛び込みたい」と思うように。そこで転職したのが、IT業界でした。
この会社には当初営業職として入社しましたが、2年ほど経った頃人材開発室が立ち上がるのと同時に異動。新卒・中途採用、人材開発、組織開発、ほかに人事評価制度など、人事にかかわる制度の改善や新設に従事しました。
そのなかで、「さらに自分を高めていきたい」という気持ちが強くなり、転職を考えるようになったんです。
「自分の思い描くキャリアを実現したい」「自分を高めたい」という想いから転職。常に挑戦し続けていますね。
もともと人材サービス会社にいたり、中途採用に携わったりするなかで、自分自身の市場価値は常に意識していたんです。特に、2社目では40代に入っていたこともあって、「プレイヤーとして手を動かしながら自分を成長させられる最後のチャンスかもしれない」という気持ちがありました。
そんな想いで転職エージェントに登録して、出会ったのがはなさく生命です。
当時のはなさく生命は、創業から4〜5年が経過したタイミング。長い目で見れば、まだまだ立ち上げ初期と言える状況でした。であれば、まだ整えられていない制度や施策の企画をしたり、立ち上げフェーズで発生している課題を解決するなど、多様な経験ができるのではないかと思ったんです。

従業員の声に耳を傾け、誰もが活躍できるよう人事施策を整える
大下さんは現在人事総務部で課長補佐を務めています。具体的にどんな仕事をしているか、教えてください。
私は人事総務部の人材開発チームで、中途採用に関する実務やキャリア形成の企画・運営に携わっています。全社イベントを企画するなど企業風土の醸成も私たちの仕事ですね。
入社以来、約1年半で10以上の施策を策定したのだとか。そのなかで、印象に残っているプロジェクトは何ですか?
1つは、キャリア形成施策の一環として策定した「はなさくラーニングプログラム」です。
企業成長のためには、ビジョンに掲げる「ニュー・インシュアランス・クリエイター」として一人ひとりが生命保険業界に新しい価値を提供する必要があります。そのためには、個々が学びを止めず成長することが不可欠。会社としてその後押しをしなければという、強い想いがありました。
はなさくは100%中途採用で、プロフェッショナルなメンバーが集まっている組織ですが、入社後その能力をさらに高め続けてもらえたらと。その個々の力が組織としての力となり、会社全体を向上させていくという好循環を生み出せたら、企業はいっそう成長できます。
そこで、資格取得に対して褒賞金を支給する制度や、各種研修を会社負担とするなど、学び支援のためのプログラムを形にしていったのが2023年度の1年間で取り組んだことです。
2024年10月にはさらに学び支援を充実させるため、これらの制度をそれぞれバージョンアップしてパッケージ化し、「はなさくラーニングプログラム」をリリースしました。
また、「制度をつくって終わり」ではなく、受講者が学んだ事を業務の中で活かせるように、インプットしたあとにアウトプットする機会をつくり、学んだことの定着を促しています。
もう1つ私にとって印象的な取り組みが、新入社員に対するオンボーディング施策です。

詳しく聞かせてください。
はなさく生命は100%中途採用。入社後早期に活躍していただくためには、不安や戸惑いをできるだけ取り除く必要があります。けれども、私が入社したときにはまだ仕組みとしてのフォロー体制は整っていなくて。たまたま私の同期入社のメンバーが率先して横のつながりをつくってくれて、とても助かったんです。
その経験から生まれたのが、四半期ごとに直近3カ月に入社したメンバーを集めて行う「フォローアップ研修」です。新入社員研修のおさらいをすることが主な目的ですが、同期同士横のつながりをつくることも大きなねらいです。従業員を「孤独」にさせたくないのと、何より横連携ができると日々の業務がスムーズになりますよね。
もう1つ、入社後6カ月が経過した人に「6カ月面談」を実施しています。環境に慣れてきた時期だからこそ感じていることや入社前後のギャップをキャッチアップする機会ですね。機能発揮できているか、部署内でコミュニケーションが取れているかなど人事メンバーが話を聞いて、問題があれば解決に動きます。
一連の施策策定の話を聞いていると、大下さんから「こんな世界をつくりたい」という強い想いを感じる一方で、「誰ひとり取り残したくない」という繊細さを感じます。
想いを形にする過程で「通ってきた道に花が咲かなくなった」ということがないように、やさしさは持ち続けたいと思っているんです。正しさを追求することも大事ですが、そればかり押し通して取り残される人が出てしまうのは本意ではありません。
だからこそ従業員の声に耳を傾け、誰もが活躍できるような人事施策を整えたい。
従業員の声は先に話した6カ月面談のほかに、定期的に実施している従業員アンケート等からも収集していましたが、それに加えてさらに本質的な組織のコンディションを把握するために退職面談を始めました。
それまでどんな理由で退職に至ったのかは所属部門との面談情報のみしか残されていなかったこともあり、「はなさくを退職する真の理由を突き止めたい」「本音の部分を聞きもらしたくない」と思ったんです。
退職理由を知って、入社前後のギャップがあるのであれば、今後入社してくる人にはそれがなくなるように手立てを打ちたいし、組織課題があるのであれば小さなうちに芽をつんでおきたい。はなさくをもっといい会社にしていくために、退職面談からもそのヒントを集めたいと思いました。
もともとはなさくは離職率自体は低いんですが、会社として伝えたいことを正しく伝えられれば従業員満足度はもっと上がるのではないか。6カ月面談や退職面談は現場の生の声を知り、人事施策の策定やアップデートにつなげる貴重な機会なんです。

景色合わせの難しさに苦悩。「健全に意見を交わせる環境のおかげで乗り越えられた」
人事施策を打つにはまず課題を把握する必要があったと思うのですが、入社してからどのように組織課題を探っていったのでしょうか。
はじめに採用業務に携わったんですが、そのなかで各部署が求める人物像や活躍イメージをインプットしたり、組織が目指すゴールとそこに向けての課題をヒアリングしたりして全体像をキャッチアップしていきました。
そうするうちに、採用ホームページがなくて転職希望者がはなさく生命の情報を十分にキャッチできないでいることや、個々の能力を伸ばすための施策をより充実させたほうがよいこと、それこそ社員同士の横のつながりが生まれればもっと仕事がスムーズになることなど、さまざまな具体の課題が見えてきたんです。
そこから1つひとつ課題の解決に取り組んでいったのですね。
そうですね。今でこそ「いろんな取り組みをしてきたな」と笑って振り返れるんですが、渦中にいるときは本当に大変でした。
どんなことがあったんでしょう。
中途採用100%でメンバーのバックグラウンドが多様なので、お互いの「スピード感」と「景色」を合わせるのにものすごく苦労したんです。
私のように異業種出身の人。生命保険業界出身の人。親会社である日本生命から出向ではなさくの立ち上げに参画した人。まずこの三者だけでも文化やスピード感は大きく異なります。さらに、同じ生命保険業界でも保険会社か代理店かで歩調が違ってきます。
そうなると、「同じ山を眺めていても、相手からは正面側を見ながら、私は後ろ側を見ながら話す」ということが起こってしまう。そもそも前提として持っている知識やスキル、価値観が異なるので、それぞれで景色の見え方が違ってしまうんです。
もちろん、各領域のプロフェッショナルが集まっているわけですから、前職までに培った価値観をもとに議論をするのはとても有意義なことです。でもそれを1つにまとめあげて新しい風土をつくっていくのは、ひと筋縄ではいかないなと。
身体も脳もヘトヘトで、「どういう伝え方をすれば、自分の想いが正しく伝わるんだろう……」と文字どおり頭を抱えて苦悩する毎日でした。
目的達成のために力だけで押し通すのではなく、周囲への気配りを忘れない大下さんだからこそ、そうした苦労も人一倍だったのかもしれませんね。その大変な局面を、どう乗り越えたのでしょうか。
とにかく丁寧な対話をすることを心がけました。もう1つ、異業種の経験がある自分に求められていることは何かを念頭に、「自分が正しいと思うこと、違和感を感じることはしっかり伝えていこう」という信念を持って、臆さず発信するようにしてきました。
それに対して、上司やメンバーはそれを頭から否定せず、まずは耳を傾けてくれる。本当に感謝しています。
リスペクトの気持ちを持ったうえで健全に意見を交わし合える、いいチームだなと思いますね。
お互いに信頼関係が醸成されていますね。
人事部門は社外の動きにも注意を払う必要があるので、異業種で人事を経験してきた私の意見を積極的に受け入れてくれている感覚があります。一方私は生命保険業界での経験がないため、メンバーがどういう想いで日々の業務に臨んでいるのか、素直に意見や助言を求める。そうした相互補完ができていると思います。
経営層とディスカッションをしていても、「大下さんの意見を聞かせてほしい」と意見を求められることがあって、人事に関していちプロフェッショナルとして扱ってくれていると感じます。
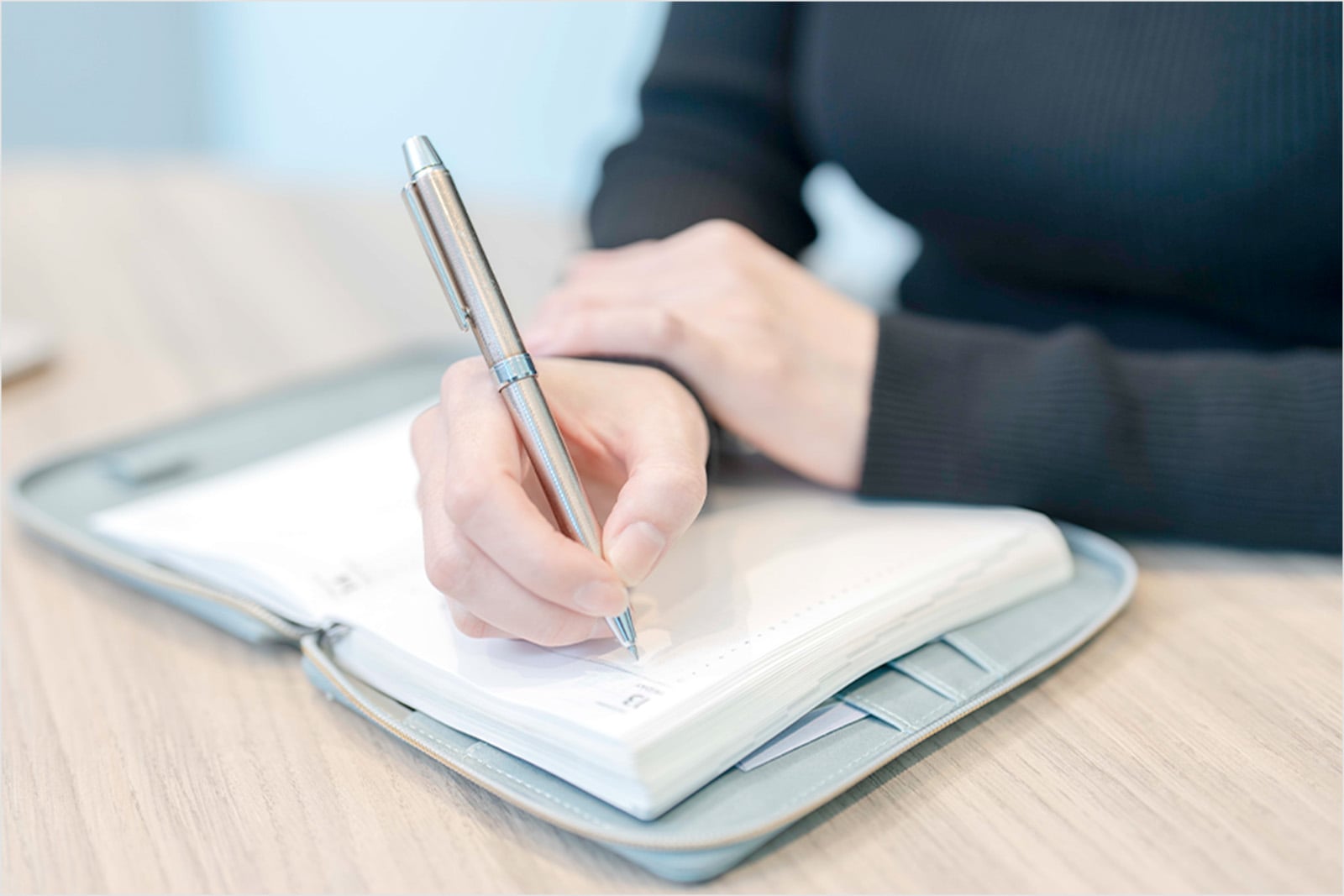
「人事にとってのお客様は従業員」その先にいる家族も幸せに
話を聞いていると、人事の仕事にとても情熱的に取り組んでいることが伝わってくるのですが、大下さんの熱意の源泉はどこにあるんでしょう。
私は「人事にとってのお客様は従業員である」と思っています。そしてその向こうには、家族やパートナー、友人など従業員を取り巻く人たちがいます。従業員が満足度高く働くことで、その周りも幸せになれる。そんな会社をつくっていきたいんです。
私自身にも娘が2人いるんですが、「お母さん、仕事楽しそうだね」と言ってもらえることが嬉しいし、久しぶりに合った友だちと仕事の近況を夢中で語り合うのも楽しくて。それが原動力になって、「次もいい仕事がしたい!」と思えます。
そう思っているのは私だけでなく、きっと周りのメンバーも同じはず。だからこそ、働きやすさや日々の仕事において自己実現ができているかを含め、いきいきと働ける環境を提供することが人事部門の使命だと思いますね。
この想いをさらに強くしたのが、2024年7月にはなさく生命として初めて開催した「ファミリーデー」というイベントでした。
このイベントには小さなお子さま連れも含め、100名を超える従業員が参加しました。私は事務局の一員として参加しましたが、一緒に働くメンバーの同僚としての顔ではなく、家族とともにいるプライベートな表情を見て、それぞれの従業員に生活が、人生があるんだなと実感しました。
人事として制度を整え、充実した職場にしたい。自分の大切な人たちに対して、胸を張って「はなさく生命は素晴らしい会社だよ」と言えるように、そして周囲の人たちから応援してもらえるような会社にしなければと、気が引き締まる思いでした。
大切な人たちと過ごす時間が仕事にも好影響を及ぼして、いい循環が生まれそうですね。
そうなんです。私自身、子どもたちに気づかされることは多くて。たとえば、仕事柄「人がその能力を発揮するには?」といった育成や能力開発について考えることが多いんですが、先日中学生の娘との雑談のなかでヒントを得ることができました。
その日娘が受けた社会の授業で、先生が「この話の内容を知っている人はいますか?」と尋ねて、誰も答えられなかったと。でも娘は実は答えを知っていたんだそうです。「すごいね!」と褒めたら、娘は「知識があってもそれを発信できなければ、知識があるとは言えないよ」と落ち込んでいて。
あらためて考えると、「ある知識や経験を持っている」と言えるのは、それをちゃんと使いこなせてこそだということをその会話から気づかされました。そんなふうに、家族との日常生活から仕事に直結する気づきが得られたり、逆に人材育成で実践していることを子育てに還元できたりしていますね。
それこそ、家族が応援したくなるような充実した職場にしたいという想いと、充実した仕事ができているからこその家族との時間、両者がバランスよく成立していますね。
子どもとこんな会話ができるのも、リモートワークができたり、フレックスタイムを利用して行事に積極的に参加できたりするおかげです。心身の健康や充実したプライベートがあってこその仕事だと思うので、今後も従業員に働きやすい環境を提供していきたいと思っています。

「プロフェッショナルに選ばれるはなさく生命」でありたい
人事の観点から、今後はなさく生命をどんな組織にしていきたいですか?
「現状維持=退化」だと思っているので、現状に満足せず、常に進化を続ける組織でありたいですね。
はなさく生命は2024年で開業から5年が経過しました。ここまで駆け抜けるように人事制度を整えてきましたが、成長期となる第2フェーズに向けて、これまで取り組んできたことの棚卸しと言語化をする必要があると考えています。
ここからさらに会社を伸ばしていくために、どのように人事戦略を立てていくか。それを考えるときに、来年、再来年という短い期間で考えるのではなく、10年先、20年先と会社が続いていくなかで、全員がやりがいを持っていきいきと働ける状態をつくっていきたいですね。
歴史はつながっているので、「過去」と「いま」をベースに未来を見据えた人事戦略のあり方を考えていくべきだと思っています。
大下さん自身が今後挑戦していきたいことを教えてください。
はなさく生命では「生命保険業界で最も働きやすく、働きがいのある会社を追求する」ことを掲げています。個人的にも、本気でそれを目指していきたいですね。
具体的には、「どんな会社でも通用するプロフェッショナルな人材が、あえてはなさく生命を選ぶ」という状態をつくりたいと考えています。
優秀な仲間と刺激し合い、自身を成長させられて、成果に対して適切な評価が得られる。人事として施策とカルチャーの両面でこうした環境を提供するために、今後も他社にない施策や制度を積極的に取り入れていきます。
社内にはさまざまなバックグラウンドを持ったメンバーがいます。各分野のプロフェッショナルの知見を融合して、ワンチームになってこうした取り組みを実現していきたいですね。
人事としても、「自分もはなさく生命のDNAを構成する1人なんだ」という気持ちで一緒にカルチャーをつくってくれる仲間に出会えるよう、発信を続けていきたいと思います。
※組織名・社員の所属部署や役職等は
取材当時のものです。


