
部門を越えて社員をつなぐ「橋渡し役」としてコミュニケーションを促し、さらなるカルチャー浸透に貢献
社内に一体感を生み出し、組織や事業の成長を促すためにも、カルチャー醸成は会社にとって大切な要素です。はなさく生命に根づくのは、「お客様にとっての最適」を考えるCXカルチャーと、プロフェッショナル同士がお互いをリスペクトし共創する姿勢。「ともに働く仲間が気持ちよく働けるようサポートするのが自分の役割」と話す統合マーケット企画部 課長補佐の髙橋佑輔に、はなさく生命のカルチャー醸成の取り組みについて聞きました。
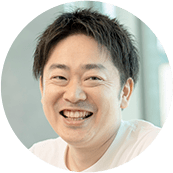
髙橋 佑輔 YUSUKE TAKAHASHI
統合マーケット企画部
課長補佐
埼玉県出身。2013年に大学卒業後、新卒で保険代理店へ入社。来店型保険ショップで保険募集を経験したのち、営業企画・推進や経営企画業務に従事。2020年10月にはなさく生命に入社し、営業企画やアライアンスとの推進、中期経営計画策定などの経営企画業務にも従事。趣味は釣りとゴルフ。
目次
- はなさく生命の商品開発やシステム改修のスピード感に感銘を受け入社
- 営業推進から経営企画まで「4つの顔」を使い分け効率よく仕事を回す
- 立ち上げ期から成長期へ。長期にわたる顧客との接点をつなぐプロジェクトに参画
- 「メンバーが気持ちよく働く環境をつくることが自分の役目」
- 業務の中でも飛び交う「CX」という言葉。顧客体験価値向上の理念が土台として定着
全て表示
はなさく生命の商品開発やシステム改修のスピード感に感銘を受け入社
髙橋さんがはなさく生命に入社した経緯を教えてください。
私は学生時代、自分がこれからどんな道を歩むにしても金融の知識があれば役に立つだろうと考えて、ファイナンシャルプランナーの資格を取得しました。それもあって、就活は当初、金融業界を中心に考えていたんです。
結果、2013年に大手保険代理店に入社しました。
金融業界のなかでも保険業を選んだのは、ある大手保険会社が発信していた「保険はいろいろな企業の挑戦を支えるインフラだ」というフレーズがきっかけです。「誰かの支えになれる保険っていいな」と感じて、就活の軸を保険業界に絞りました。
複数の保険商品からお客様のニーズに合った商品を提案できる代理店の仕事がしたいと思って、ご縁のあった保険代理店に入社することにしました。
当時はどんな仕事をしていたんですか?
入社後は保険ショップで保険商品の販売を経験し、その後本社の営業企画部に異動。当時110店舗ほどあった保険ショップでの販促キャンペーンの企画や、既契約者向けの販売促進活動など、お客様の来店を促すための施策立案などをしていました。
ほどなく、店舗の業績管理や、販売動向から販促商品を決めて現場に展開するといった、より内勤的な業務にシフト。6年目には社長直下の経営企画部で、中期経営計画の策定や事業報告の作成を担当するなど、経営戦略に近い領域を担うようになりました。
はなさく生命に入社したのは2020年10月ですが、何が転職のきっかけになったのでしょうか。
はなさくの商品開発のスピード感やシステム周りのすぐれたUI/UXに感銘を受けたんです。
前職では2019年6月にはなさく生命の商品を扱い始めたんですが、あっという間にシェアを伸ばして同年内に社内トップシェアに躍り出ました。代理店側から見ても、はなさくの商品競争力は「すごいな」と。
ただ、当時は前職でさまざまな仕事を経験させてもらっていたし、不満もなかった。転職をするつもりはなかったんです。
そこに、新型コロナのパンデミックが起きました。
それまで、実際にお客様にお会いして保険募集するのが当たり前だったものが、オンライン面談等で保険募集をするサービスを求められたりするなど、世の中の働き方やお客様へのサービス提供方法が大きく変化しました。そうした実感もあり、世の中の変化に対応できるだけの柔軟性とスピード感が今後とても重要であると感じました。
そんなとき、たまたま転職サイトを見ていたらはなさく生命の求人が出ていたんです。はなさくの、お客様のニーズにもとづいた商品供給やシステムの利便性・わかりやすさなどの事業拡大のスピード感を、肌身で感じていたので、「これは!」と思い応募して、ご縁をいただきました。

営業推進から経営企画まで「4つの顔」を使い分け効率よく仕事を回す
現在はどんな業務に携わっていますか?
現在は、「統合マーケット企画部」「経営企画部」「エージェンシーマーケット推進部」「ダイレクトマーケット推進部」と、4つの部署を兼務しています。
統合マーケット企画部は、一般的な企業でいうと営業企画部と呼ばれる部署です。はなさく生命には営業部門として2つ、代理店営業を行うエージェンシーマーケット推進部と、お客様に直接保険商品を販売するダイレクトマーケット推進部があります。
この2つの営業部署のバランスを取りながら、全社収支のトップラインやボトムラインをいかに上げていくかや、当社の強みを活かしながら、生命保険会社としての認知・ブランディングをいかに向上させていくかを考えるのが統合マーケット企画部の主な役割です。特に最近は、ご契約者様へのサービス強化も新たな経営課題として、関係部を巻き込みながら取り組んでいます。
また、NTTドコモ社との協業(dポイント還元商品の供給)やクレジットカード会社など顧客基盤を持っている企業と提携して保険販売を広げるアライアンス関係の模索・構築も大切な業務です。提携先企業の本業を棄損することなく、各企業の会員様に対し、どういった付加価値の提供を目指し、保険を訴求するためにどんな手段が有効か、加入プロセスをどう引くべきかなどを提携先企業と議論して進めています。
部署を4つ掛け持ちしているんですね。
そうなんです。特に経営企画部の兼務は、中期経営計画の策定などの業務にも携わることで、より多角的な視点で物事を考えられる機会をいただき、大変やりがいを感じています。

立ち上げ期から成長期へ。長期にわたる顧客との接点をつなぐプロジェクトに参画
立ち上げフェーズから成長フェーズに移行しつつあるはなさく生命。髙橋さんは直近で、どんなプロジェクトに携わっていますか?
2024年4月に「ご契約者様へのサービス強化に関するワーキンググループ」を立ち上げ、事務局として参画しています。
はなさく生命は開業から5年が経過し、「ご契約者様をいかに増やすか、はなさく生命という会社をどのようにお客様に知っていただき、気に入っていただくか」ということに加えて、「ご加入いただいたご契約者様にいかに長くご契約継続していただくか」という点も、これまで以上に重要になっています。なぜなら、「保険」という商品は、長く続けていただくことによって初めて、いつ発生するかわからないさまざまなリスクに対し、保障を提供できるものだからです。
お客様に長く(永く)お付き合いいただくためには、ご契約時やご契約後の顧客体験も重要です。かつ、代表的な生命保険会社のように、自社の営業パーソンがいない当社において、お客様にどのようなサービスや情報を提供すればお客様の心をつかみ続けることができるか。
こうしたことを営業部門や契約保全周りを担当するCS戦略部を中心に、幅広い部門を巻き込みながら、ワーキンググループで推進しています。
事務局として、具体的にどんな役割を担っているのでしょう。
全体の方向性や各施策の進捗状況の確認、施策案の検討などですね。具体的には、たとえば中期経営計画の目標として掲げる数値を作成して、それを達成するために何をどう改善すべきか、ゴールと時間軸を示すなどしています。
具体的な施策については、保険代理店や新しいお客様との接点をもち、現場をよく知る営業部であったり、ご契約者様と直接接点をもちながら、お客様サービスを企画するCS戦略部であったりと一緒に検討して、PoCを実施しています。
施策にかかわる各部門や経営層など、ステークホルダーの多いプロジェクトですね。
だからこそ、施策の目的や背景、目指すべきゴールをしっかりと共有しておくことが大切だと感じていますね。
事務局の役目としてはもう1つ、ゴールに向けて各部門がどういう位置にいるか進捗を把握して、適切な対応を促す必要があります。そのためにはコミュニケーション力が必須ですね。
たとえばある部門の業務の進捗が芳しくない場合に、何がボトルネックになっているか確認して、相手が自走できるように事務局として伴走する必要があります。このとき、相手としっかりとコミュニケーションを取って、悩みを取り除けるよう寄り添うことが大切です。
実験的な取り組みやさまざまな部門とのコミュニケーションを含め苦労も多そうですが、反面、やりがいも大きそうですね。
そうですね。当社収支のボトムライン向上に向けては、当プロジェクトが重要な取り組みとなるため、大きなやりがいを感じていますし、施策の1つにお客様とデジタル上でコミュニケーションするプラットフォームを立ち上げる構想があります。これは「デジタルの利便性」と「有人対応によるヒトの温かみや安心」を織り交ぜることで、長きにわたってはなさく生命を愛してくれる「ファン」をつくる。ハードルの高い取り組みですが、同時に将来性やダイナミックさを感じていますね。
この取り組みに向けて各部門やりたいことはそれぞれあるので、うまく調整しながら課題を解決していかなければなりません。大変な仕事ですが、その先に「はなさくが好き」と言ってくださるお客様が増えるのであれば、こんなうれしいことはありませんね。

「メンバーが気持ちよく働く環境をつくることが自分の役目」
日々の業務に取り組むうえで、髙橋さんはコミュニケーションやホスピタリティをとても大切にしている印象です。
そうですね。さまざまな業務をこなせるのは、私自身が専門的な知識やスキルを有しているわけではなく、各部門の仲間の力を借りられるからこそだと思っていて。
エージェンシーマーケット推進部、ダイレクトマーケット推進部の専門知識を持ったメンバーが気持ちよく効率的に働けるようサポートすることが自分の役割だと思っているので、楽しく円滑に働いてもらえるようにホスピタリティを持って接したいんです。
ホスピタリティといえば、髙橋さんは全社朝礼でエンターテイナーな一面をのぞかせていますよね。
そうですね。そもそも全従業員の皆さんの前で、お話しする機会をいただけていることに感謝の気持ちです。毎月の全社朝礼で行っている業績報告は全従業員に関係するものなので、「会社がいまどんな状態なのか」に少しでも興味を持って聞いてもらえるよう心がけています。
結果的にそれが新たなコミュニケーションを生むきっかけにもなっていますね。
たとえば、どんなことがありましたか?
こうした機会をいただくことで、それまでコミュニケーションを取ったことのなかった他部門の人からリアクションが届いたり。
連絡をくれたことがきっかけでつながった人には、その後気軽に声をかけやすいなど、自分の仕事にもプラスになっています。
ひと工夫ある朝礼は、カルチャーの醸成にも一役買っていそうですね。
はなさく生命はさまざまな業界からの中途採用が多く、中でも保険会社や代理店、銀行など金融業界出身者が多い。金融業界ですと、堅いイメージをされる方もいるかと思いますが、服装もカジュアルだし、雰囲気もやわらかく、非常にフラットな企業風土だと思います。何より社長室がなく、社長が社員と同じフロアの椅子に座っているんですよ。
そんな物理的な「カベ」もない組織なので中途入社のメンバーが初めて朝礼に参加したときに、「はなさくってこんな雰囲気なんだ」と肌で感じる一助になればと思いますね。

業務の中でも飛び交う「CX」という言葉。顧客体験価値向上の理念が土台として定着
開業から5年、そもそもなぜはなさく生命にはうまくカルチャーが浸透しているのだと思いますか?
いまいるメンバーは、はなさく生命の立ち上げ期に、はなさく生命という新しい会社で、この業界をより良くしたい、という想いをもってきた人たちばかりです。そして、今後も引き続き、はなさくには「世の中に新しい価値を提供するんだ」というチャレンジ精神を持った人たちが参画してくるでしょう。
こうした志の高いプロフェッショナルなメンバーがお互いをリスペクトしながら組織を構成するからこそ、文化が浸透していくのではないでしょうか。
もう1つは、2022年をCX元年として、従業員1人ひとりがボトムアップでお客様の顧客体験価値(CX)を追求しているからではないかと思います。
詳しく聞かせてください。
顧客体験価値は以下の3つの価値で形成されていると考えています。商品やサービスと価格のバランスから感じる満足感である(交換価値)と、各種手続き等で感じる利便性・安心感(使用価値)、お客様が企業との接点や利用経験を通じて感じた企業イメージ・共感(文脈価値)です。一方で交換価値は、商品競争の激化に伴い、差別化することが難しくなってます。なので使用価値・文脈価値が大きな差別化となると考え、2022年、統合マーケット企画部内に「CXチーム」を設けて、CX向上のためのさまざまな取り組みを開始しました。
若手を含め各部門で「CXアンバサダー」を任命してもらっているんですが、CXチームとCXアンバサダーが協力して社内外の業界問わず良かった顧客体験・悪かった顧客体験などを集めて毎月レポート『CX REPORT』にまとめています。
そうした体験を見ると、こんな些細なことで満足感を感じるんだという気付きにもなっています。
反対に不満を感じた体験の共有もありますので、それに対し、「この場合のCXをよりよくするにはどうしたらいいか?」をフリーコメントしてもらうなどして、社員がCXについて考える仕掛けを盛り込んでいます。
こうした取り組みを感じて、実際にCX向上に対する意識は高まっていると感じますか?
はい。何か1つの案件を検討するうえでも、1人ひとりが「これを受け取ったお客様はどう感じるだろうか」を考えるようになってきていると感じますね。社員のなかでCXに関する「気づき」が育っているように思います。
ふだんの業務の中で「CX」という言葉が飛び交うこともありますね。
たとえば、ご契約者様へのサービス強化に関するワーキンググループで「お客様との接点を持つために電話をしたらどうか」という議論が出たときに、「そのタイミングで電話をするのはCXの視点でどうだろう」という会話が自然に出てきます。
1つひとつの施策を考えるうえで、収益の観点だけでなく、お客様満足度の観点で見たときにどうかという文脈で会話がなされるのを聞いて、CXカルチャーが土台として定着してきていると感じますね。
しっかりと土台ができてきているんですね。それを踏まえて、髙橋さんのなかでは今後はなさく生命がどんな組織になることが理想ですか?
はなさく生命は、中途採用者が多くさまざまな文化や経験を持つ人が集まる貴重な「財産」を有していると思っています。こうした前職での貴重な経験を、お互いリスペクトし合い、部門を越えて、より活発に議論ができるよりよいカルチャーが根付いていますので、今後事業拡大とともに組織が大きくなる中でも維持され、より活発になるようにしていきたいですね。
会社が成長し、規模が大きくなるにつれて、他部門が何をしているか、どんな課題を抱いているか、見えづらくなっていきます。
私は業務上、いろいろな部門のメンバーと会話する機会がありますし、その分たくさん情報を得られます。そうした業務上の特性を活かして、組織のカルチャーの橋渡し役を担っていけたらと思っています。
※組織名・社員の所属部署や役職等は
取材当時のものです。


