
「年齢関係なく『誰もが主役』になれる」若手開発者が語る、はなさく生命開発チームで働く醍醐味
顧客体験価値の向上と事業の成長をシステム領域で支える、はなさく生命の開発チーム。「30年後のシステムをレガシー化させない」ことを開発思想とし、お客様の利便性に貢献するためのシステム開発に日々取り組んでいます。「はなさく生命では、年齢に関係なく誰もが主役になれる」と話すのは、CS戦略部開発チームで課長補佐を務める福井啓太。若手のなかでも第一線で活躍する福井に、開発組織としてのプロジェクトの進め方や仕事の醍醐味について聞きました。
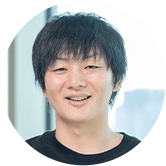
福井 啓太 KEITA FUKUI
CS戦略部 課長補佐
2011年新卒から、生命保険のシステム開発事業に従事し、代理店用の提案書や申込システム、新契約査定システムの開発プロジェクトを経験。2022年にはなさく生命に入社し、Salesforceを活用したコールセンターシステム等の開発に従事。
休日は本気のテニスで汗を流し、トーナメントでの優勝経験も多数あり。現在は更なるレベルアップを目指し、下半身トレーニングを強化中。
目次
- はなさく生命への入社の決め手は人と雰囲気。「フィーリングがぴったり合った」
- ビジネス部門に寄り添い、システムの企画から開発まで幅広い領域に対応
- プロフェッショナルたちが主体性を持って臨むからこそのスピード感と正確性
- 30年後の開発チームのために「レガシー化させない」システム構築を心がける
- 誰でもがチャレンジできる環境「いずれビジネス的視点で自らシステムの企画・提案を」
全て表示
はなさく生命への入社の決め手は人と雰囲気。「フィーリングがぴったり合った」
福井さんははなさく生命に入社する以前、どんな仕事をしていましたか?
前職までは、新卒で入社した生命保険会社のシステム子会社に10年ほど勤めていました。代理店スタッフが提案書をつくる際に使用するシステムや、保険料試算システムの開発に2〜3年ほど、あとの期間は生命保険の新契約査定システムの開発に携わっていました。
転職を考えるようになったきっかけは、キャリアアップがしたいと思ったためです。ずっとシステム開発に携わってきたので、「何か新しいことがしたい」と考えるようになりました。
当時転職の軸としたのは、これまでの経験を活かして即戦力として働けて、かつ、キャリアアップできる環境であること。
はなさく生命を知ったのは、転職エージェントを通じたスカウトメッセージがきっかけでした。ほかにもいくつか生命保険会社が候補に挙がっていたんですが、はなさくは「ほかとはちょっと違うぞ」と思ったんです。
どんなところが「ほかと違う」と感じたんですか?
ほかの生命保険会社は、ビシッとスーツを着込んで仕事をしている人が多く、堅めの雰囲気。面接でもこれまで携わってきた業務実績を確認する質問が多かったですね。
一方はなさくは、面接というより雑談をしているようなムードで、過去の実績よりも「人としての考え方」や「大事にしていること」など、パーソナリティに迫る質問が多く、親しみを感じました。
業務の内容はどの生命保険会社も似通っていましたが、人や雰囲気の部分でもっとも「フィーリングが合うな」と感じたのがはなさく生命だったんです。
もう1つ、面接してくれたのは僕とそう年齢の変わらない方たちだったのですが、どちらも課長職に就いていて。「こんなに若くても課長として活躍できるんだな」という、いいイメージを持てたことも、入社の後押しになりました。

ビジネス部門に寄り添い、システムの企画から開発まで幅広い領域に対応
現在はCS戦略部内の開発チームに所属していますが、具体的にどんな業務に携わっているのでしょうか。
CS戦略部の開発チームは、経営企画部や統合マーケット企画部、コールセンターなど社内のさまざまな部門から挙がる「こんなシステムをつくりたい」という要望に応え、システム開発を行っています。
僕自身は現在Salesforceを使って、コールセンターでお客様対応の際に活用するシステムの企画・開発を担当しています。
コールセンターではどのお客様から電話があったか、そのお客様に対しどんな資料を発送したかなどの情報をSalesforce上に蓄積して管理しています。僕たちはコールセンターのメンバーが使いやすい機能の検討や改善案の提案を行い、Salesforceに機能を追加したりしています。
はなさく生命では通常、社内の開発チームが画面表示の仕方などシステムの仕様を決めて、その後実際に手を動かして開発する部分は外部の開発パートナーに業務委託することがこれまでのシステム開発の中心でした。
ですので、僕のように内製化してシステム開発をしているケースは社内でもまれですね。Salesforceはカスタマイズがしやすいサービスなので、開発スピードの向上やコストカットのためにも自分たちで手を動かすところまで対応しているんです。
そのなかで、福井さんはどんな役割を担っていますか?
主にはビジネス部門と一緒に、システムの企画などを行っています。それ以外にも、実際に手を動かしてシステムを変えるところから、正しく動作するかどうかのテスト、リリース作業やトラブル対応まで、幅広い領域を担当しています。
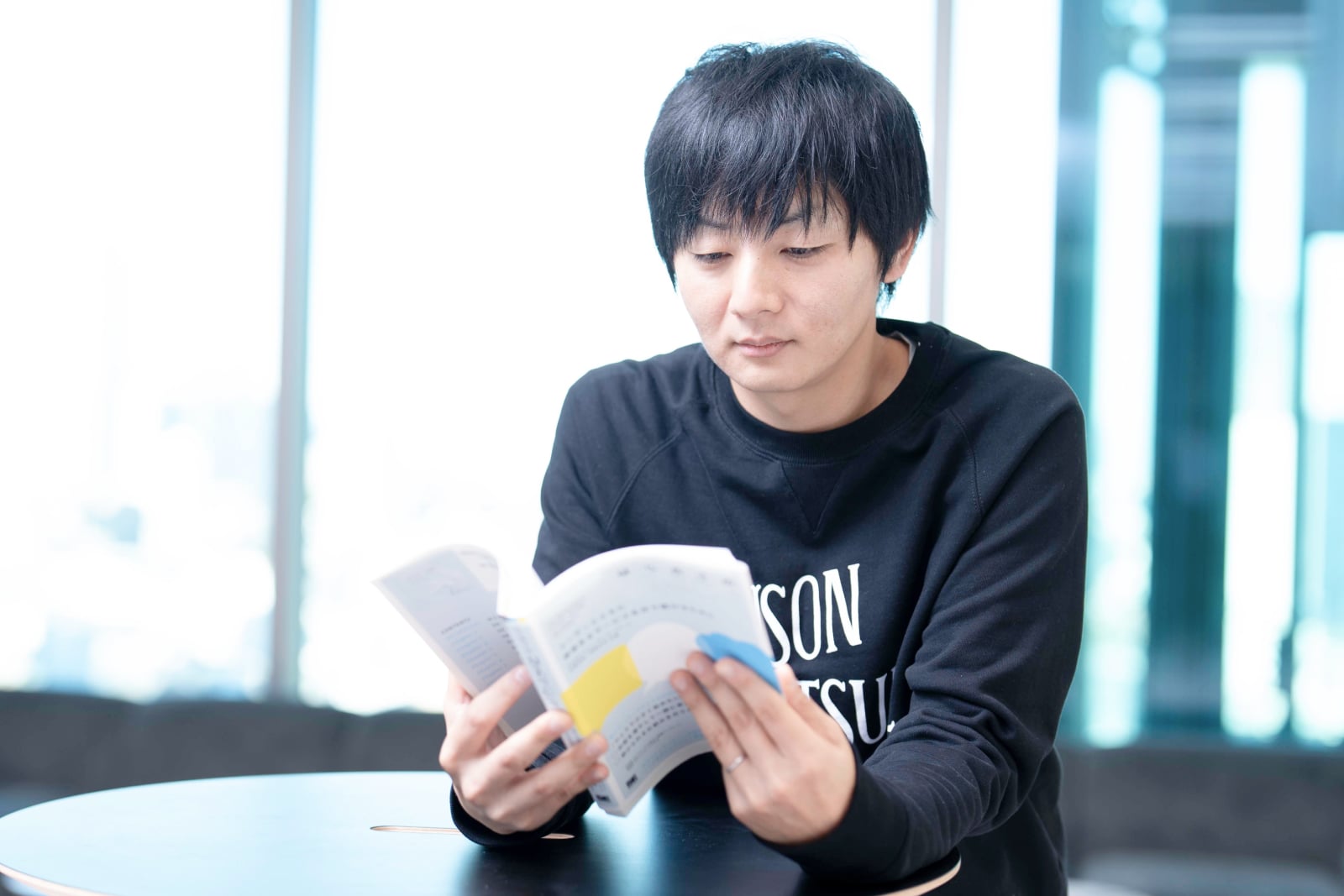
プロフェッショナルたちが主体性を持って臨むからこそのスピード感と正確性
これまで携わったプロジェクトで印象に残っているものを教えてください。
はなさく生命では2024年10月、LINE公式アカウントを利用したお客様向けサービスを開始しましたが、このときのシステム開発のプロジェクトが印象に残っています。
そもそもLINE公式アカウントは、お客様とのコミュニケーションの接点を増やすために開設しました。
これまでお客様とのコミュニケーション手段といえば、電話によるコールセンターとのやり取りが中心。けれども、電話は忙しい人にとってはハードルが高く、接点を持ちづらいという課題がありました。
そこでLINEの公式アカウントを開設して友だち登録を促進するとともに、友だち登録をしてくださったお客様のアカウントとSalesforceに蓄積された顧客データを紐づけるシステムを開発し、お客様とはなさくとのコミュニケーションを活性化しようという試みです。
お客様の利便性向上につながるプロジェクトですね。
そうですね。はなさくには、どうしたらお客様の体験価値(CX)を向上させられるかを社員一人ひとりが考える「CXカルチャー」があります。
このCXを考えるためのツールとして、月1回「CX REPORT」というレポートが社内で発行されているんですが、もともとこのレポートの中で行われたアンケートで「LINEを活用してはどうか」という提案があったんです。
そこからこのLINE公式アカウント施策の可能性を探り、統合マーケット企画部が中心となってプロジェクトに取り組むことになりました。
私たち開発チームは実務を運用するコールセンターの部門と一緒に、要件定義の段階からプロジェクトに参画。その後、実際に画面の設計などをする段階でIT部門や外部の開発パートナー数社にも入ってもらって、プロジェクトを推進していきました。

それぞれの部門の役割分担はどうなっていたのでしょうか。
統合マーケット企画部が案件リーダーとして窓口に立つ以外は、各システム領域の担当者がフラットにそれぞれの持ち場で開発を進めていくイメージですね。
一般的なシステム開発で想起されるような、プロジェクトオーナーがいて、リーダーがいて、コスト担当、スケジュール担当などが縦割りで割り振られて……というきれいなプロジェクト管理体制はあえて採っていませんでした。
よくある縦割り型のプロジェクト管理体制にしなかったのは、スピード感を出したかったから。縦割りのカベを取っ払ったほうがスケジュールも早く進行するし、コミュニケーションも円滑になると判断したんです。
統合マーケット企画部がはなさく生命のLINE公式アカウントをどう運用するかを考え、僕はコールセンターの人たちがLINEを活用するために、Salesforceの画面上で顧客情報とLINEアカウントをどう紐づけるかをメインに担当していました。
縦割りで役割分担をせずに進めると、各領域がお互いに「ここは相手がやるだろう」と思い込むことによる抜け漏れが発生しがちだと思うんですが、それはなかったんですか?
確かに、一般的なプロジェクト管理体制よりも今回のようなフラットな組織のほうが、いわゆる「お見合い」による抜け漏れリスクは発生しやすいはずですよね。にもかかわらず抜け漏れを防ぐことができたのは、それぞれの領域で「自分たちが何をすべきか」の確認を怠らなかったことが挙げられます。
あとは、プロジェクトチームが少数精鋭であることも抜け漏れが発生しない要因の1つですね。チームの人数が多ければ人任せになる人も出てくるでしょうが、少人数だとミスがダイレクトに自分に跳ね返ってくる。むしろ「しっかり責任を持って業務に取り組まなければ」という意識が働きますね。
少人数だとミーティングもセッティングしやすいので、コミュニケーションもしっかり取れる。お見合いによる落球を潰しやすいんですよね。
プロフェッショナルたちが集まっているからこそできる体制といえそうですね。
そうですね。主体性があるメンバーが集まっているからこそ、こうしたプロジェクト管理体制が成り立つんだと思います。はなさく生命には、プロジェクトを自分事として考える主体性の高い人たちが多いと感じますね。
システム開発にはよくある話ですが、このプロジェクトでも開発が進むにしたがって想定していなかった仕様や製品側の制約が判明して、急な仕様変更が必要になりスケジュールが遅れそうになることがありました。
そんなときも、各領域の担当者に相談すると、どうにか解決しようと一緒に知恵を絞ってくれる。ベストな答えが導き出せるまで徹底的に議論できる環境でした。誰かがリーダーシップをとらなくても、自然と領域を超えて助け合う姿勢がありましたね。

30年後の開発チームのために「レガシー化させない」システム構築を心がける
福井さんは、はなさく生命で働くやりがいやおもしろさをどんなところに感じていますか?
はなさく生命は設立してから間もないこともあってシステムが軽く、さまざまな製品やクラウドサービスとつなぎやすい点が魅力ですね。
歴史ある企業だとレガシーなシステムがパッチワーク状につなぎ合わされて、柔軟性に欠ける状態になっていることもしばしばで。新しいことをやりたくても、つなげる製品が限られたり、もはや新しく製品をつなぐ余地がなかったりといったことがあります。
その点、はなさくのシステムはかなり軽く作られているので、新システム導入の際、やりたいことを実現するために最適なシステムを自分で選定するところから、実際に導入するところまでやりきれる点にやりがいを感じますね。
なるほど。でもそれだと、年数が経てばいずれはなさく生命のシステムもレガシー化してしまうのでは……?
そうならないように、システム開発の際は「将来的に禍根を残しそうな対応をしていないか」を常にレビューするようにしています。
たとえば大きなシステムの開発に携わる際に、「レガシー化するようなつくり込みをしていないか」「属人化していないか」といったチェック項目があって、それをすべて満たすシステムをつくるよう開発方針が立てられているんです。
30年後の人たちが困らないように、「レガシー化させない」ことを文化として受け継いでいこうとしているんですね。
そうですね。開発チームにはもう1つ、「本当に必要なものだけをつくる」という理念もあります。
ビジネス部門の皆さんにシステムで何を実現したいか聞くとどうしても、「あれがしたい」「これがしたい」という前向きな気持ちによって、その時点でマックスの要件が並ぶことになります。
開発チームとしてはできるだけそれらの要望に応えたい。けれども、すべてを言われたままにつくってしまうと、思ったよりも使い勝手がよくなかったり、既存のシステムと機能がかぶってしまったりして、そのうちに使われなくなる「もったいないシステム」が生まれる可能性があります。
だから、企画の段階で「なぜこのシステムが必要か」「いまやるべき開発か」を自分自身でしっかりと問い、その目的や理由に納得してからプロジェクトを進めるという方針を採っています。
「そのシステムが必要かどうか」を判断するうえで大切にしていることは何ですか?
要望を出している相手の業務を、きちんと理解すること。そして、相手がどんな課題を抱えているか、もしくはどんな目的を達成したいのかを理解することです。
相手と同じくらい、相手の業務や課題を理解する。そのためには、とにかく相手に質問をして、「なぜやるか」を深掘りするようにしています。その内容と開発チームの開発思想とを照らし合わせたうえで、その開発をいまやるべきか、優先順位を下げて取り組むかを判断するようにしていますね。

誰でもがチャレンジできる環境「いずれビジネス的視点で自らシステムの企画・提案を」
ここまで話を聞いて、福井さんは若手メンバーながら大きな裁量を持って仕事をしていると感じます。
そうですね。主体性があれば、裁量を持って仕事できる環境だと。システムの開発をするときも、先ほどのLINE公式アカウントの例のようにビジネス部門から「これがやりたい」と声が挙がるパターンもあれば、自分たちで「これに取り組む必要があるのではないか」と提案して導入に至るパターンもあります。
そうした意味では、はなさく生命は若手、ベテランなど年齢に関係なく主役になれる環境だと思いますね。
会社によっては、主体性があってもその上のカベに阻まれて先に進めないことがありますが、はなさくにはそのカベがなく、若くしてプロジェクトを引っ張っている人が多い。主体性のある人が押しとどめられることなく前進していけます。
もしもカベに当たったとしても、何度も試行錯誤してそのカベを乗り越えようとする。そんな粘り強さと行動力のある人が多い印象ですね。
チャレンジのしがいがある環境ですね。今後はどんなことに挑戦していきたいですか?
2022年に入社して約2年、はなさく生命のシステムの全体像がハッキリと見えたので、次はそのシステムをどう使えばはなさく生命を発展させられるのか、ビジネス的な視点をもって日々の業務に取り組んでいきたいと思っています。
これまで統合マーケット企画部やコールセンター部門が取り組んできたような、事業やサービスを起点としたシステム開発の提案ができるようになりたい。開発チームから社長に向けて「このシステムを使ってこんな施策を打てばお客様数を増やせますよ」という提案ができるようになればカッコイイですよね。
そうしたビジネス的視点をどう身につけていきますか?
ビジネス部門のメンバーと密に会話することで学びに結びつけることが1つ。もう1つは、実際に現場でどんな実務が行われているか、たとえばコールセンターに直接足を運んで現場の仕事を自分の目で見て確認することですね。
コールセンターにとっては日々のルーティンワークとして取り組んでいることも、僕たち開発者の視点から見ると「こんな大変なことをしているのか」「効率化できそうだな」と感じる工程があるかもしれません。
課題を人づてに聞くのではなく、その場に赴いて自分の目で見つけにいくことで、ビジネス的視点を養いたいですね。業務理解や課題把握に関しては、現場のメンバーに聞けば快く教えてくれるので、積極的にコミュニケーションを取っていきたいと思います。
システム側の視点とビジネス側の視点、両方を身につけられたら強みになりそうですね。
そうですね。今後、他部門と連携してプロジェクトを進行する際、エンジニアリングに関してはもちろん、しっかりと現場のことを把握したうえで他部門との検討や調整をすることは必須だと思っています。
現場のことを深く知り、それをシステムにつなげられるような仕事がしたいですね。
※組織名・社員の所属部署や役職等は
取材当時のものです。


